【第一章:天職と、見えない代償】
大学時代の恩師は、僕たちにこう言った。 「君たちは、分子の指揮者だ」と。
一つ一つは自由奔放な分子たちに規律を教え、最高のハーモニーを奏でさせる。 途方もなく大変で、けれど、どうしようもなく魅力的なその仕事に、僕は夢中だった。
大学院まで探求した、そんな化学の世界。 それは、僕の天職のはずだった。
地元が好きで、この街で家族と暮らしたくて選んだ会社で、僕は夢中で働いていた。 しかし、そんな僕に命じられたのは、頻繁な海外出張だった。 高校時代から付き合い、やっと一緒になれた妻と、また離れ離れになる日々。
皮肉なことに、そんな海外出張の中で、僕が開発した製品は大きな評価を得てしまう。 クライアントに認められる高揚感と、「成功すればするほど、大切な人から遠ざかるかもしれない」という静かな恐怖。 光と影が、僕の心の中で渦を巻いていた。
『家族は、いつまでもそこにいるわけじゃないんだ。』
■ 僕の心を、凍らせた、二つの出来事
・突然の、別れ。祖母の死。
そして、その「静かな恐怖」が、ある日突然、現実の形となって僕の胸を抉ることになる。 祖母の、突然の死だった。
身近な人の死に初めて触れた僕は、頭を殴られたような衝撃を受けていた。
それは、あまりにも残酷で、でも、目をそらせない現実だった。
もし、海外にいる時に、妻や、両親に何かあったら…? その時、自分は、本当に大切な人のそばにいてあげられるのだろうか。
キラキラしていたはずの仕事の成功が、少しずつ、その色を失っていくのを感じていた。
・尊敬する先輩との、語らい。そして、転勤
僕の中で無視できないほど大きくなっていく不安の正体を確かめたくて、僕は、信頼する会社の先輩を食事に誘った。 4つ歳上で、同じ職場で違う材料を研究している、尊敬できる先輩。
ちょうど家を建てたばかりだと聞いていたから、そのお祝いと、僕自身が抱える将来へのモヤモヤ、そしてマイホームへの憧れ。色々な想いが、ごちゃ混ぜになっていた。
しかし、先輩の口から出てきたのは、僕が予想もしなかった言葉だった。
「俺、九州に転勤になったんだ。」
耳を疑った。家を建てたばかりなのに? その言葉は、僕の頭の中で、遠い記憶の引き金を引いた。 そうだ、僕の父親も、家を建ててすぐに、単身赴任になったんだった。
『ライフステージが変わるタイミングで、辞められないように転勤させる』 会社にまつわる黒い噂が、背筋を凍らせるほどの現実味を帯びて迫ってくる。
寂しそうに笑いながら、先輩は言った。
「知らない間に子供が大きくなって、知らない間に新品だった家が古くなっていくんだろうな。子どもが付けた傷も、その瞬間を見ていない俺にとっては、ただの傷だ。思い出に、ならないんだよな…」
先輩のその一言は、僕がぼんやりと感じていた恐怖の、一番見たくない核心を、容赦無く突き刺した。
仕事の成功とは、一体何なんだろう。 僕が本当に守りたいものは、何なんだろう。
もう、見て見ぬふりは、できなかった。
【第二章:人生の岐路に立った日】
そんな僕の心を追い詰めるように、会社の上司たちが飲み会の席で笑いながら話している言葉が、耳に突き刺さった。
「来年あたり、にゃっくるに海外に駐在してもらって…。」
それは、まだ正式な辞令じゃない。 でも、日に日に増えていく海外への出張が、その言葉がただの冗談ではないことを、僕に嫌というほど突きつけていた。 大好きな実験もできなくなる。そして何より、やっと一緒になれた妻のそばにいられなくなる。 僕の心は、もう限界だった。
■ 妻との、運命の対話
ある夜、僕は妻に、震える声で想いをぶちまけた。 「会社を辞めたい」じゃない。
「どうしよう」
と。情けない、ただのSOSだった。
すると妻は、僕の情けないSOSを、ただ静かに、全部受け止めてくれた。 そして、ふわりと微笑んで、こう言ったんだ。
「…そっか。そんなに辛かったんだね。…もう、やめても、いいんじゃないかな。」
僕が情けなくおどおどと、
「でも、生活が…。」
と、つぶやくと、彼女は、芯の通った、優しい声で続けた。
「大丈夫。私、公務員だし、なんとかなるよ。」
そして、少しだけ、いたずらっぽく微笑んで、こう付け加えた。
「それにね、公務員の仕事って、言われたことをやるだけだから、楽だよ?今の仕事よりは、絶対にね。」
妻のその言葉が、最後のピースだった。 それまで僕の心の中でバラバラになっていたパズルのピースが、まるで分子の指揮者(コンダクター)が最高のハーモニーを奏でるように、ぴたりと、一つの答えを導き出した。
そうだ。僕が一番大切にしたいものは、研究でも、キャリアでもない。 この人だ。この人と、この街で、一緒に生きていくことだ。
■ 人生を賭けた、試験勉強
「よし、公務員になろう。」
決意は、固まった。 でも、その時すでに、僕は28歳。 公務員試験の年齢制限、30歳まで、あと2年しかない。
仕事を辞めて、専門学校に通い、2年間、死に物狂いで勉強するか? でも、もし2回続けて落ちたら…?収入も、キャリアも、すべてを失うことになる。 僕の人生を賭けた、あまりにも大きな、大きな選択だった。
それからの日々は、まるで出口の見えない、暗いトンネルの中を歩いているようだった。 答えなんて、すぐに出ない。 仕事を辞めて、退路を断つほどの勇気も、まだ持てなかった。
毎日、夜11時過ぎまで続く残業。断ることのできない、海外への出張。 心も体も、もうとっくに限界を超えていた。 でも、僕は、悶々としながらも、ペンを握った。
空港のロビーで、次のフライトを待つ時間。 海外へ向かう、飛行機の中の窮屈な座席。 そんな、人生のほんの僅かな「隙間」だけが、僕に許された勉強時間だった。
『まずは、働きながら1年やってみよう。もしダメだったら、最後の1年で、きっぱり会社を辞めて、専門学校に行こう』
そう自分に言い聞かせても、心の奥底から、最悪のシナリオが何度も顔を出す。
『もし、それでも受からなかったら…?』
その恐怖が、鉛のように、僕の肩にのしかかっていた。
そんな、潰れそうになる僕の心を、何度も何度も救ってくれたのは、妻の言葉だった。
「大丈夫。私がいるよ。もしダメでも、私が働いてるから、なんとかなる。」
その言葉が、僕にとって、唯一の光だった。
正直、試験そのものの記憶は、あまりない。 会社には内緒で進めていた転職活動だったのに、一次の筆記試験、そして二次の面接。そのどちらの前にも、まるで僕の覚悟を試すかのように、必ず海外出張が入れられた。
土曜の朝、始発で空港から試験会場に直行し、前夜に無理やり5次会まで連れ回された酒の匂いをさせながら、ボロボロの頭で問題用紙に向き合ったことだけを、覚えている。
■ 運命の、最終面接
そして、運命の最終面接。 目の前に座る副市長が、僕にこう問いかけた。
「君のやってきた化学と違って、公務員は人を扱う。教科書通りにはいかないが、大丈夫かね?」
その瞬間、僕の中で、何かがプツリと切れた。
『なんだこいつ。何も知らないくせに、僕が人生を捧げてきた化学を、バカにするな。』
気づけば、僕はこう言い返していた。
「大丈夫です。ご存知ないかもしれませんが、教科書に載っているのは、すでに知られた事実です。僕たちの仕事は、日々、未知のものに向き合うこと。イレギュラーへの対応力なら、誰よりも自信があります。」
部屋の隅で、人事課長が必死に笑いを堪えているのが見えた。 後から聞いた話では、副市長はカンカンだったらしい。 でも、総務部長が「あのくらい尖ったやつを採らないとダメですよ。」と、僕を猛プッシュしてくれたのだという。
…もっとも、僕が一番入りたかった地元の市役所の試験は、2回とも落ちてしまったのだけれど。
そして、僕は、妻とは違う市役所の職員として、新しい人生のスタートラインに立つことになったのだ。
【第三章:僕が本当に手にしたかったもの】
■ 理想と現実
人生を賭けた試験を乗り越え、僕は公務員になった。 ようやく手に入れた、家族との、穏やかな未来。 …そのはずだった。
僕が配属されたのは、市役所の中でも群を抜いて残業が多いと言われる「総務課」。 選挙の調整、条例の制定…。触れたこともない法律と、他の課の偉い人たちに、毎日もまれ続けた。
月の残業時間は、当たり前のように80時間を超えた。ひどい時には、200時間を超えることもあった。
そんな時、妻の妊娠がわかった。 『今度こそ、家族のそばに』 そう思って相談した育休は、お世話になっている上司の、
「制度上は、とれるよ(ニコッ)。」
という一言の前に、儚く消えた。
初めての出産で、妻が一番辛いであろう時期に、僕は家に帰れない。 長男を、この腕に抱く時間すらない。
僕の頭の中は、ぐるぐると、同じ言葉が回り続けていた。
『あれ…?仕事は簡単で、言われたことをやるだけじゃ、なかったっけ…?』
手に入れたはずの未来は、僕が思っていたものとは、少しだけ、違う色をしていた。
■ 一つの幸せと転機
大変な日々が続いていたある日、僕たちに一つの転機が訪れた。 長男の誕生を機に、新しい家を建て、僕も部署を異動することになったのだ。 配属されたのは、市役所内でも比較的穏やかだと言われる「環境保全課」。
ようやく穏やかな未来が手に入る…!と期待したのも束の間、その実態は「仕事をしない職員の掃き溜め」と揶揄される場所だった。
やるべき仕事は、誰もやらないまま山積みになっている。 僕は、その部署で出会った一人の尊敬できる上司と共に、結局、泥にまみれて働く毎日だった。
希望が見えない日々の中、妻の二度目の妊娠がわかった。
『この部署なら、今度こそ…!』
幸い、直属の上司や課長は「ぜひ、前例を作ってくれ!」と、僕の背中を押してくれた。 しかし、最後の壁として、補佐が立ちはだかった。
「君は良くても、次の課長が『男の育休なんてサボりだ』って言う人だったら、僕がどう説明するんだ?」
その一点張りで、僕の願いは、何度も何度も、跳ね返された。 しかし、神様は、まだ僕を見捨ててはいなかったらしい。 翌年、その意地悪な補佐自身が、課長に昇進したのだ。 彼が恐れていた「パワハラ上司」が現れる可能性は、彼自身の手によって、消え去った。
そうして僕は、1年という希望には遠く及ばないものの、当時としては男性で最長となる「2ヶ月」の育児休暇を、ようやく、その手に掴み取ったのだ。 長男の時には、叶わなかった想い。 それは、僕にとって、何にも代えがたい、勝利だった。
■ 眠れない夜に、見つけた新しい「地図」
その思いを強くしたのは、思わぬ発見だった。 新しい家族の登場に、当時3歳だった長男が、見えない不安を抱えていたこと。 日中、その不安な気持ちを受け止めてあげられる大人が、妻一人ではなく、僕もいる。
親が二人いるという安心感を、いつでも彼に与えてあげられたことが、何よりも、育休を取って良かったと思えた瞬間だった。
もちろん、良いことばかりじゃない。 次男は、夜中に何度も泣き、しょっちゅう風邪をひいた。 幸い、ミルクが好きでいてくれたおかげで、夜中の授乳は僕が代わることができた。
妻を休ませてあげられる。その喜びと同時に、僕は、世の中の母親たちの、本当の凄さを知ることになる。
2時間おきに、容赦なくやってくる授乳の時間。 連続して眠れない辛さ。 僕がうとうとしている間に、この小さな命に何かあったら、という漠然とした恐怖。
もちろん、やることは無限にある。洗濯、掃除、ミルクの準備。 でも、育児とは不思議なもので、猛烈に忙しい時間と、赤ん坊が眠って、ふっと訪れる静寂の時間が、交互にやってくる。
腕の中の息子が寝息を立て始めると、僕も、次の戦いに備えて、少しだけ休息の時間に入るのだ。
この、静かで、でもどこか落ち着かない時間の中で、僕の人生を変える一本のLINEが届いた。
前の会社の友人からだった。 彼も家を建てるところで、お金に困っている、と。 雑談の流れで、彼は僕に「NISA」という制度を教えてくれた。
『株』
その言葉が、僕の頭の中で、突然、閃いた。 もともと、麻雀のようなギャンブルは好きだった。 でも、いつ泣き出すか分からない赤ん坊の隣で、集中力が必要なゲームなんてできない。
でも、株なら…? これなら、次男を見ながら、ほんの少しのスリルを味わえるかもしれない。
それは、子供のため、なんていう立派な動機じゃない。 寝不足の父親が、退屈を紛わすために見つけた、ほんのささやかな「娯楽」。 それが、僕と、株式投資との、本当の出会いだった。

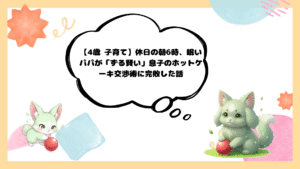

私の、X(旧Twitter)では、日々の、もっとリアルな、つぶやきを発信しています!ぜひ、フォローしてくださいね

コメント